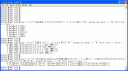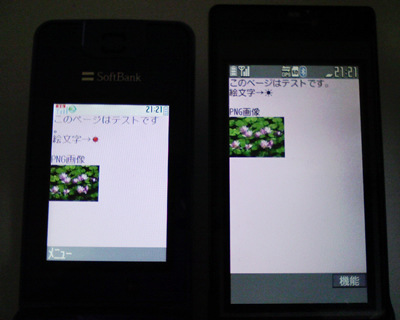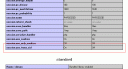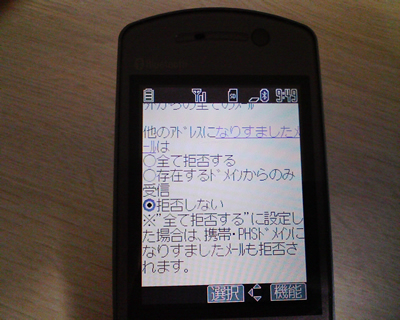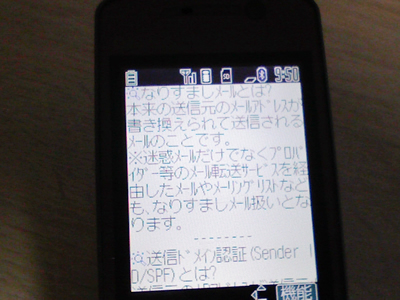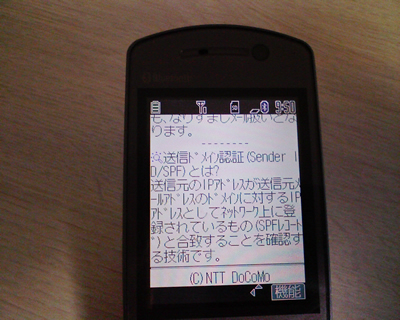mod_chxjは、ユーザエージェントから端末を判断し、絵文字や画像の3キャリア変換を自動処理するApacheモジュールです。
先日のこちらの発表で、なぜか今頃になって注目を浴びつつあるこのソフトをインストールしてみました。
mod_chxjは、2006年7月のバージョン0.8.0からリリースがありません。
今後、メンテナンスされるかどうかも不明で、端末データも古いです。
今回はとりあえず評価目的ということで、インストールから動作するところまでご紹介しようと思います。
こちらのサーバの環境としては、
「CentOS5 + Apache2.2(httpd-2.2.3-11.el5.centos)」
となっています。環境が違う方は適宜読み替えてください。
ドキュメントはこちらにありますので、これに沿って作業していく形になります。
→ mod_chxj ドキュメント [sourceforge.jp]
まずは動作に必要なソフトをインストールします。
ドキュメントによると次のものが必要なようです。
mod_chxjをインストールする前に、下記のものを用意する必要があります。
1. Apache2.0のヘッダーファイル群
2. Apache2.0用のapxs
3. apr(Apache Portable Runtime)ライブラリとそのヘッダファイル郡(apu含む)
4. automake、autoconf、libtool1.3.X
5. ImageMagick(MagickWand)
6. libiconvまたはlibiconv_hook
yumを使って順にインストールしました。
# yum install httpd-devel
# yum install automake autoconf
# yum install libtool
# yum install ImageMagick
# yum install ImageMagick-devel
# yum install pcre-devel
libiconvはyumになかったため、こちら [gnu.org]からダウンロードしてインストールしました。
$ ./configure
$ make
# make install
さてこれで準備が整ったので、次はmod_chxj本体のmakeなのですが、私の環境ではApache2.2系を使っているため、このままコンパイルしても通りません。
2.2系を使っている場合は、先にパッチを当てる必要があります。
2.0系の方はそのまま行けると思います。
パッチはこちらのサイトを参考に作成させていただきました。ありがとうございました。
→ Devel::Bayside mod_chxj を Apache 2.2 で動かす [hatena.ne.jp]
パッチのダウンロードはこちらからどうぞ
→ mod_chxj-0.8.0_apache2.2_patch.tar.gz [ke-tai.org]
$ tar xvfz mod_chxj-0.8.0.src.tar.gz
$ cd mod_chxj-0.8.0
※以下Apache2.2系の方のみ
$ patch src/mod_chxj.c < ../mod_chxj.c.2.2.patch
$ patch src/chxj_cookie.c < ../chxj_cookie.c.2.2.patch
mod_chxjのコンパイルとインストール
$ ./buildconf.sh
$ ./configure --with-apache-header=/usr/include/httpd/
--with-apr-config=/usr/bin/apr-1-config
--with-apu-config=/usr/bin/apu-1-config ※実際には1行で実行
$ make
# make install
CentOS5の場合は、なぜかaprとapuに「-1」がついていたため、上記のオプションをつけました。
環境によっては不要になると思います。
詳しくは「./configure –help」でご確認ください。
これで「/usr/lib/httpd/modules/mod_chxj.so」にモジュールがインストールされました。
続いて端末データと絵文字データの置き場所を作り、データコピーします。
# mkdir /etc/httpd/chxj
# cp etc/device_data.xml /etc/httpd/chxj/
# cp etc/emoji.xml /etc/httpd/chxj/
mod_chxjの設定ファイルを作成します。
# vi /etc/httpd/conf.d/chxj.conf
内容は次のようにしました。詳しくはmod_chxjのドキュメントページをご覧ください。
# Load module mod_chxj
LoadModule chxj_module /usr/lib/httpd/modules/mod_chxj.so
# Device data
ChxjLoadDeviceData /etc/httpd/chxj/device_data.xml
# Emoji data
ChxjLoadEmojiData /etc/httpd/chxj/emoji.xml
設定が正しいか確認します。
# apachectl configtest
ここで、
httpd: Syntax error on line 210 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Syntax error on line 2 of /etc/httpd/conf.d/chxj.conf: Cannot load /usr/lib/httpd/modules/mod_chxj.so into server: libiconv.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
のようなエラーが出る場合は、libiconvのライブラリが読み込めていない可能性があります。
ひとまずシンボリックリンクを張ってごまかしましょう。
(何かスマートな方法がありましたら教えてください)
# ln -s /usr/local/lib/libiconv.so.2 /usr/lib/
エラーが出なくなったらApacheを再起動します。
# apachectl configtest
Syntax OK
# /etc/init.d/httpd restart
httpd を停止中: [ OK ]
httpd を起動中: [ OK ]
これで動作準備OKです。
続いてmod_chxjの設定を書きます。
httpd.confに書いても良いのですが、私は.htaccessに書くことにしました。
mod_chxjを動作させたいディレクトリに、次の内容で.htaccessを置きます。
<IfModule mod_chxj.c>
ChxjConvertRule ".+$" "EngineOn" "NONE"
ChxjImageEngine On
</IfModule>
HTMLを設置しケータイから確認すると、確かにドコモからは見れないはずのPNG画像が表示されています。
またソフトバンクでは絵文字の変換も行われているようです。
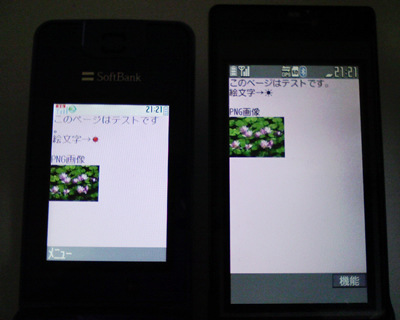
関連:








 Flash プロの現場の仕事術 CS5/CS4/CS3対応
Flash プロの現場の仕事術 CS5/CS4/CS3対応 体系的に学ぶ 安全なWebアプリケーションの作り方
体系的に学ぶ 安全なWebアプリケーションの作り方 ケータイHTML ポケットリファレンス
ケータイHTML ポケットリファレンス 携帯サイト年鑑2010
携帯サイト年鑑2010 PHP×携帯サイト デベロッパーズバイブル
PHP×携帯サイト デベロッパーズバイブル 携帯サイト制作 WEBデザインの新しいルール
携帯サイト制作 WEBデザインの新しいルール ケータイHTMLコンパクトリファレンス
ケータイHTMLコンパクトリファレンス
 札幌のソーシャルゲーム開発なら
札幌のソーシャルゲーム開発なら